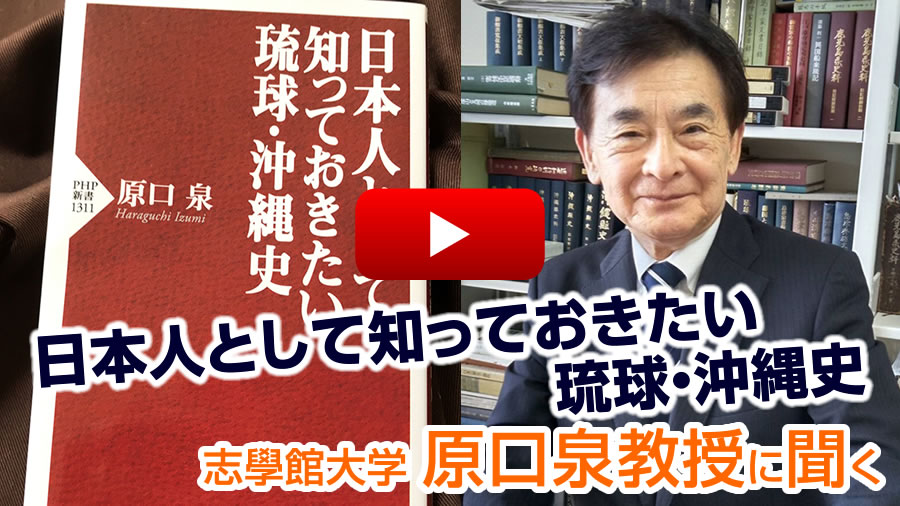義母のうちの庭の柿の木が今年は大豊作!甘柿、渋柿、たわわに実って、嬉しいやら、あまりの多さに困惑するやら…毎週夫と、のこぎりと高枝切狭で格闘し、たくさん収穫しました。
大小まちまち、傷があったりと粒ぞろいではないものの、ご近所におすそ分けしたり、お料理に活用したりとここ数か月、柿三昧の毎日。義母や母と一緒につくった干し柿づくりは、忘れられない思い出になり、その味も最高でした。
柿の木オーナーは、不二子おばあちゃん
これまで不二子おばあちゃんの名で「てのん」で度々ご紹介してきた義母89歳。畑仕事が大好きで、自分で育てたヘチマでお手製のヘチマ水を作ったり、ドクダミの花と焼酎で虫刺され治療の自家製塗り薬を作ったりとその暮らしぶりは自然そのものです。

その義母は、昨年体調を崩して、足腰が弱くなり、畑仕事ができなくなってしまいました。高齢の義母の安全な生活を守るためとはいうのもの、殺風景になってしまった庭を見るたびに切なくなっていました。すると夏の終わりの頃、思いがけない義母からの一言が…「美規代ちゃん、庭に冬瓜が生ってるみたいよ!まだ、小さいけど秋になったら採ろうね。」「えっ?いつの間に植えたの?」
畑からの思いがけない贈り物…冬瓜のおはなしから
義母はいつも調理した後に出る野菜くずを、水分を切って庭に埋めています。冬瓜が生ったのは、その生ごみを埋めている場所のあたり。「夏にヘルパーさんが冬瓜のお料理を作って下さったから、その種が生ごみの中に混じっていて、育ったんじゃないかね。」とニコニコ顔。
冬瓜の種が、発芽して、花を咲かせ、実をつけて、人知れずひっそりと育っていたようです。近くの木々を頼りにツルを伸ばして、小さいながらも瓢箪のような形をした可愛らしい冬瓜が育っていました。
何という生命力!生ごみから生まれた冬瓜!これぞ究極の暮らし中のSDGs!今年できた、たった一つの収穫物でしたが、食べることよりも育てることが大好きな義母にとっては思いがけない畑からの贈り物だったようで、冬瓜を大切そうに握りしめていました。

冬瓜は、定番の豚肉とショウガの煮物にしておいしくいただきました。そして、もう一つの畑からの贈り物が、柿の大豊作でした。
不二子おばあちゃんちの柿の木のおはなし
義母の後ろに写っているのがその柿の木。20年ほど前に甘柿を植えて、そのあと5年くらい経ってから、その隣に渋柿の種を蒔いてみたら、仲良く並んで大きくなっていったそうです。「桃栗3年、柿8年」という言葉がありますが、10年ほど経ってから柿が実をつけるようになりましたが、特別な剪定をするわけでもなく、生ったら、採りやすいところだけ収穫して食べたり、渋柿は、熟して渋が抜けたものを少しだけ食べて、あとは鳥さんたちに食べてもらっていたそうです。
「今年はすごいね。こんなに生ったのは初めてだよ。」と義母。「(渋柿で)吊るし柿を作ってみようか。」という義母の提案で、干し柿づくりに挑戦することになりました。義母もこれまで干し柿を作ったことはないそう。見よう見まねの干し柿づくりが始まりました。
「とりあえず柿をとってきま~す。」と私。試しに庭から、渋柿を数個、採ってきました。

初心者マークの干し柿づくり
「あら、あら。枝を全部、切り落としゃったのね。枝を残しておいた方が、紐を引っ掛けやすかったんだけどね。でも大丈夫!大丈夫!」最初から失敗してしまった私ですが、義母が柿のガクの部分に器用に紐を引っ掛けて、「こんな感じでどうかな?」とお手本を見せてくれました。
「やったことないけど、人のおうちの軒下に吊るしてある柿を見ていて『あ~こうやればいいんだなあって思ってたのよ。』とにっこり。何でも自己流でできちゃう不二子おばあちゃんの本領発揮です。
「ほら、こうして繋げて、軒下に吊るしておいてみようよ。」10月下旬、鹿児島では、よく晴れた寒い日が続きました。乾燥と寒風は、おいしい干し柿づくりには欠かせません。しかも義母の家は高台にあって、風通しも良く、干し柿をつくるのに格好の条件です。
一週間ほど経ったら、ふっくらトロ~リ、半生状態のあんぽ柿みたいな干し柿が出来ていました。
「ん~おいしいよ。渋も抜けてて、甘いよ。たくさん生っているから、美規代ちゃん、好きなだけ持って帰って、お家でつくってごらん。」ということで、ここから本格的な干し柿づくりが始まったのです。
毎週、どか~ん!渋柿の山
毎週、30個くらいずつ採りました。

柿を採るのは夫の仕事。普段、畑仕事には縁のない夫が、高枝切狭で柿の実と格闘している姿は、何とも微笑ましかったです。では、初心者マークの干し柿づくりをご紹介しますね。干し柿づくりで一般的に用いられているのは渋柿の方です。
渋柿は、渋があってそのままでは食べることができませんが、もともとの糖度は、甘柿よりもずっと高く、干し柿をつくるのに向いています。干すことで渋抜きされ、甘みも凝縮され、糖度が上がって、よりおいしい干し柿ができるのです。甘柿よりもカビにくい点も、干し柿に適していると言われています。
準備するもの
渋柿 30個程度
柿を吊るす紐
(2個ずつ吊るす場合は、紐の長さは1本60~70㎝程度にしました)
ピーラー、包丁、ハサミ、ザル
助っ人が、もうひとり!92歳の母も仲間入り
収穫した渋柿をザルに入れて、いろいろ準備していると、近くに住む母も「何しているの?」と興味津々。「一緒にやろうか。」ということになりました。もともと手仕事が大好きな母。しかも干し柿は、大好物!母も92歳にして、初めての干し柿づくりとあって、ウキウキしています。
義母のアドバイスやネットなどで調べたつくり方を参考にして作ってみました。
干し柿づくりの手順
- 柿の皮むき
まず、ハサミで柿のガクの部分を切って、皮をむきます。ヘタのまわりの皮をクルッとむいて、そのあとは柿の皮を縦方向にむいていくとやりやすかったです。ピーラーを使っても便利。ふたりで、せっせとむいていきました。 - 紐つけ
全部むき終わったら、適当に間隔をあけながら、紐に柿を結びつけていきます。確かに、柿の枝の部分をT字に残しておいて、そこに輪にした紐に引っ掛けていくと、とても簡単にできました。麻ひもを使うと、もっと便利です。縒りを緩めて、できた輪っかの中に柿の枝を入れていくだけなので、あっという間にできました。
1回1回、要領が良くなっていくものです。干した時に、重さが均一になるように、柿は1本の紐に偶数個ずつ繋いでいきました。
- 熱湯に5~10秒浸して、殺菌
そして、干す前にやっておきたいことが、熱湯に浸すこと。これをやっておくと細菌の発生を防いで、カビが生えにくくなるそう。柿の色が黒ずむのも抑える効果もあるそうです。あまり長く浸けると煮えてしまうので、5秒から10秒くらい熱湯に浸して、さっと引き上げます。終わったら、間をおかず、すぐに干していきます。
- 柿を干す
雨の当たらない風通しの良いところに吊り下げます。私は、ベランダの物干し竿に吊り下げました。雨は大敵なので、室内に簡単に取り込めるように、洗濯物干しハンガーに吊り下げる方もいらっしゃるようですよ。生活の知恵ですね。柿がくっついて当たらないように(カビ防止のため)上下にずらしながら掛けていきました。
「乾燥」と「寒さ」がおいしい干し柿づくりには欠かせません。いつものベランダが、冬の風物詩に彩られて、ちょっと嬉しい気分になりました。どんな干し柿ができるかな?晴れの日が続きますように…毎日、軒下を見るのが楽しみになりました。


干し柿って生き物みたい
丸々っとして生々しかった柿の表面に、だんだんしわしわが出てきて、少しずつ小さくなっていきました。


こうして乾燥させることで、渋柿の苦みのもとであるタンニンが、可溶性から不溶性に変わって、口の中で溶けなくなり(渋抜きされ)渋が、糖に変わっていくのです。自然の力が生み出す不思議な化学反応に驚かされます。しかも、お日さまにあてて、じっくり干すことで、甘みはギュッと凝縮されて、その甘さは、砂糖の1.5倍にもなるんだそうです。一週間ほど経つと、実がひとまわり小さく、表面がザラザラした感じになって、乾いてきているのが分かります。
ここでもうひと手間。
- 柿を揉む
干してから1週間から10日ほど経って、表面がしっかり乾いてきた頃、柿の一つひとつを指でつまんで優しく揉みほぐしていきます。こうすることによって、外は甘くても、中に渋が残っているといったムラを防ぎ、早く、甘くおいしくなるそうです。食感も均一になって、種離れも良くなるそうです。
うちの干し柿は、大きかったり小さかったり、いろいろで、大きい柿の中には、内側がまだ固いものもあって、渋が抜けるには、もう一息というものもありました。強く揉みすぎると、表面が破れてしまうので、柿の状態に合わせて、やさしく揉んでいきました。
それから5日から一週間くらいたった頃、また柿を揉みます。この頃になると、柿の中心部まで柔らかくなって、しっかり揉み切ることができました。


雨の日は、ビニールを上からフワッと被せて、雨から守ります。ここまでくると生き物を育てている感覚になっていました。

柿の種類や大きさ、お天気にもよりますが、干してから2~3週間ほど経つと渋が抜け、おいしく食べられるようになってきます。この時は、まだ果肉が柔らかくてジューシー、干し柿と生柿の間のような状態です。

水分がまだ多く残っているため長期保存には向きませんが、大きくて食べ応えがあって、中のトロッとした食感がたまらないと、このくらいの干し柿が好きな人も多いですよね。うちの家族もしっかり干したものよりも、このトロ~リ半生の方が好きなので、今回の我が家の干し柿はここで完了!ということにしました。


さらに干して(1か月~40日くらい)枯露柿(ころがき)に
干し柿は、「福を『かき』こむ」縁起物としてお正月飾りにも使われています。うちでも毎年、干し柿を飾っているのですが、来年のお正月用に、長期保存に向いている枯露柿(ころがき)も作ってみることにしました。半生の干し柿をさらに干し続けて、1ヵ月から40日くらい天日干しします。

水分がかなり抜けてきますので、実は硬くて、さらに小さくなっていきます。水分が蒸発した分、甘さは凝縮されていきます。

寒風にしっかり晒して、乾燥が進むと、柿の表面には、白い粉が吹いてくるそうです。これは、糖分が結晶化したもので、ギュッと甘みが詰まっている証なんだそうです。鹿児島のうちの軒下では、この状態まではできませんでしたが、あまりヨボヨボにならないうちに、頃合いをみて取り込みました。

干すタイミングを変えながら、自分好みの干し柿をつくれるのも手づくりならではの楽しみですね。
「食べるのがもったいないみたいだねえ。」と愛おしそうな母。

自家製干し柿は、とびっきりのおいしさ!

食してみると…それはそれは、おいしかったです!(自分でつくったせいもあるのですが…)中はトロトロ、手のひらに収まるほどの小さな干し柿の中に、素朴で自然な甘さがギュッとつまっていて、しみじみ、しあわせな味でした。和菓子の世界で「甘さは干し柿をもって極上とする」という言葉があるそうです。その言葉の意味が分かったような気がしました。
干し柿づくりでお天道さまが身近に…
今年の冬、初めて挑戦した干し柿づくり。1度に30個くらいずつ、6回くらいに分けて作りました。思いがけず義理の母、母、夫も参加することになり、みんなで手分けしての共同作業となったので、一人でやるより楽しくできました。
そういえば、みんなでこんな風に一緒に何かするってこと無かったな。庭の柿は、大小さまざまで、傷があったり、形もいびつだったりして、仕上がりもまちまちでしたが、小さいものは小さいなりに、不格好なものは不格好なりに、愛着が湧いてきました。「干し柿が甘くなるかな~」と思ったら寒い日も楽しみになり、お日さまや雨を気にしながらの毎日は、お天道様をとても身近に感じられる日々でした。


お正月用に、冷凍庫に保存しました
できあがった干し柿は、その都度食べたり、ご近所さんにおすそ分けししたりして、あとは、お正月用に冷凍保存しました。干し柿は、ドライフルーツで日持ちのするイメージがありますが、長期保存にはあまり向かないそうです。
気候にもよりますが、よく干したもので、風通しの良いところに置いて3日~4日程度(乾燥防止のため紙袋やキッチンペーパーに包んで置いておくと良いそう)中がトロリとしたジューシーな干し柿は、常温保存には向かないそうです。1個1個ラップに包んで、ジップロックなどの密封できる袋に入れて冷蔵庫で1ヶ月くらい、冷凍保存すると3ヶ月くらいは大丈夫だそうです。ということで、残った干し柿は冷凍保存にしました。

ちびっこ干し柿と大ぶり干し柿とに分けて、ストローでしっかり空気を抜いて冷凍庫に入れました。お正月にみんなで食べられた良いな。冷凍保存してもカチカチには凍らず、自然解凍すると割とすぐに食べられるので、ちょこちょこ食べてしまっています。
お正月までに食べ終わってしまわないようにしなくっちゃ。
1000年以上前からあった干し柿
干し柿の歴史は、甘柿よりも古く、平安時代中期に(927年)、祭礼用のお菓子として使われていたという記載が残っているそうです。1000年以上前のはなしです。すでにこの頃から、渋を抜く方法が見出されて、貴重な食べ物として生かされていたのですね。
先人たちの智恵から生まれたドライフルーツが、途絶えることなく、今も愛され続けていているって嬉しいですね。しかもつくり方は、古来変わらず、寒風とお日さまの光にいっぱいあてて、天日干しするという至ってシンプルなもの。飽きのこない天然の味わいも不変です。
干すことで、生の柿にたくさん含まれているビタミンCは失われてしまうそうですが、栄養価が高く、登山の携帯食としても人気だとか。食物繊維やビタミンAも豊富に含まれるそうですから、バランスよく取り入れたら、子どもや高齢者のおやつにも良さそうですね。
作ってよし♪食べてよし♪干し柿のことが、ますます好きになりました。