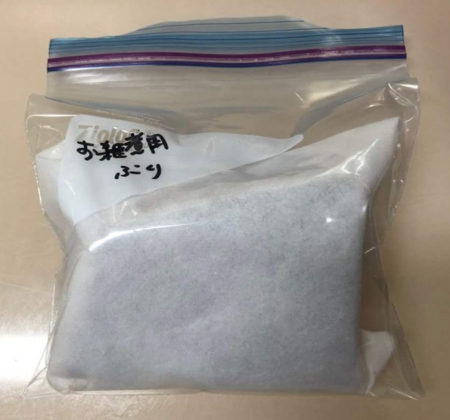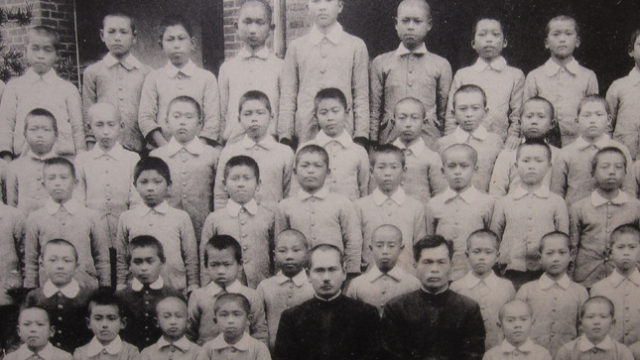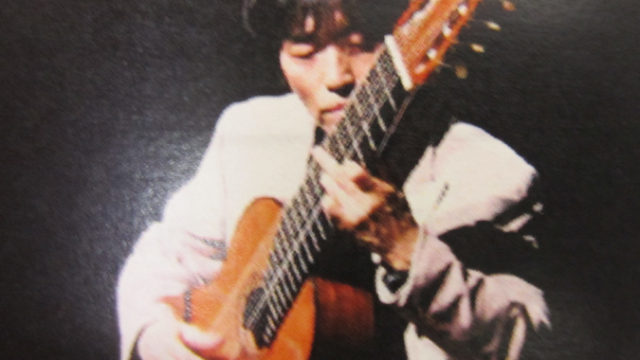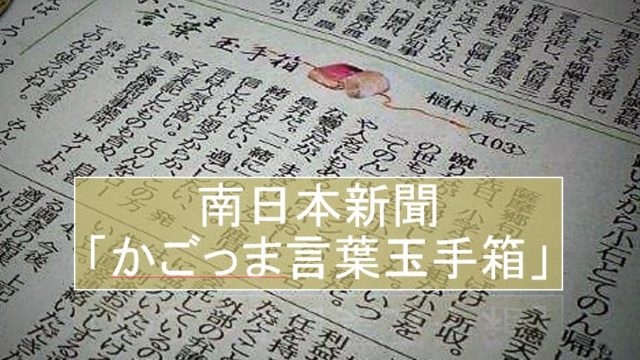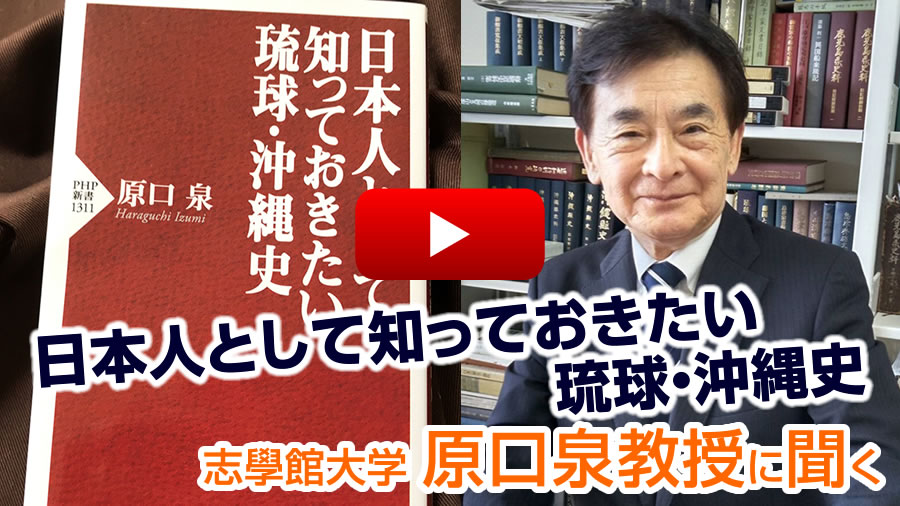2019年、新しい年が始まりました。
「てのん」の活動を始めて1年半。お伝えしてきた記事も200を超えました。
「猪突猛進」とはいきませんが、「継続は力なり」で今年もじっくり丁寧に「いま、伝えたい」ことを言葉にしていけたらと思います。
今年も「てのん」をどうぞよろしくお願いいたします。
 お正月料理に出されるお雑煮。全国各地、それぞれ地方によって、だしの取り方や具材に特徴がありますが、同じ九州でも鹿児島と福岡では作り方がけっこう違います。
お正月料理に出されるお雑煮。全国各地、それぞれ地方によって、だしの取り方や具材に特徴がありますが、同じ九州でも鹿児島と福岡では作り方がけっこう違います。
福岡の友人が作る「博多雑煮」と、我が家で作る「薩摩雑煮」を比べてご紹介します。
博多雑煮の作り方
年末年始、福岡のスーパーには「かつお菜」が山盛り並べらます。
この「かつお菜」、博多に古くから伝わる野菜で、高菜の仲間です。
漢字では「勝男菜」と書くことから、縁起物として福岡のお正月には欠かせない野菜だそうです。
福岡の友人の家では、プランターにかつお菜を植えて、正月に収穫できるようにしています。

では、福岡の友人の家で作られてきた「博多雑煮」を紹介します。
まず出汁(だし)は、焼きあご(とびうお)で取るのが博多雑煮の特徴です。
焼きあごと昆布を一晩水につけて出汁をとります。

次に具材として欠かせないのが出世魚といわれる「ぶり」。
大きめの切り身の「ぶり」にたっぷり塩をまぶして一晩冷蔵庫で寝かせます。
そして翌日、ぶりを切って熱湯でさっとゆでます。

他にも、具材として鶏肉、焼き豆腐、かまぼこ、干しシイタケ、かつお菜が入ります。
かつお菜は、さっとゆでて4センチ幅に切ります。
別の鍋で丸餅をゆでます。出汁を取るときに使った昆布を鍋の底に敷くと、餅が鍋にくっつかないそうです。
そして焼きあごでとった出汁に干しシイタケのもどし汁を入れ、薄口しょうゆ・塩等で味を整え、すまし汁を作ります。
その中に、ぶりや鶏肉、焼き豆腐などの具材を入れて煮ます。

お椀に具材を盛りつけ、汁を注ぎ入れたら「博多雑煮」の完成です。
具材は各家庭によって若干違いがあるそうですが、焼きあごで出汁を取り、かつお菜とぶりを入れるのが博多雑煮の特徴です。
鹿児島では雑煮の餅は焼くのが一般的なので、ゆでた餅を入れるのにも驚きました。
友人の親せきで鹿児島に嫁いだ方がいるそうですが、鹿児島には「かつお菜」が売られていないので、福岡から送ってもらっていたそうです。
やはり小さい頃から食べてきた故郷のお雑煮を作りたいという気持ちがありますよね。
逆に私は、福岡に来て20年になりますが、鹿児島のお雑煮を作りたいので毎年「焼きエビ」を鹿児島から送ってもらっています。
次は、鹿児島のお雑煮を紹介します。
薩摩雑煮の作り方
鹿児島のお雑煮は「焼きエビ」で出汁を取るのが特徴です。
えびはおめでたい食材なので、お雑煮の盛りつけに使う地域は他にもあるそうですが、焼きエビで出汁を取るところは、全国的にもあまりないそうです。
鹿児島では、お正月のお雑煮に欠かせないものとして焼きエビが売られていますが、福岡ではなかなか手に入りません。
実家では、焼きエビの他に干しシイタケ、昆布を入れて、一晩おいて出汁を取っていたので、私も同じように作ります。

そして、出汁に薄口しょうゆ等で味付けし、すまし仕立ての汁を作ります。
具材は、各家庭で少し違いがあると思いますが、里芋、豆もやし、人参、春菊、紅白かまぼこを用意します。
出汁に使った焼きエビと干しシイタケも雑煮の具材に使います。
- 干しシイタケは、軸を落として飾り切りをしておきます。
- 里芋、人参は柔らかくなるまでゆでておきます。
- 豆もやし、春菊は、さっとゆでます。
エビは腰が曲がるまで長生きするように。
里芋は子孫繁栄、そして豆もやしはまめまめしく元気に働けるようにという願いが込められています。
実家では、里芋は切らずに丸ごと一個、お椀の中に入れ、その上に、焼き餅をのせていましたので、私もその通りに盛りつけます。
そして、焼きエビや人参、紅白のかまぼこをお餅の上に飾り、汁を注いだら鹿児島のお雑煮の完成です。
香ばしい焼きエビの出汁のきいた、小さい頃から食べてきているお雑煮の味です。
鹿児島では昔から出水沖で「ケタ打瀬漁」が行われ、クマエビがたくさん獲れていました。それを焼いて干し、かつては島津家に高級食材として納められていたそうです。
毎年、鹿児島市の仙厳園で、お正月限定で販売される「島津家伝統の焼海老雑煮」の焼きエビはお椀からはみ出るほどの大きなものです。
しかし、この出水の焼きエビは、現在ではなかなか手に入らない高級食材。一般的には小ぶりな赤山エビなどの焼きエビを使っています。
福岡に住んでいながら、今回、初めてきちんと福岡と鹿児島のお雑煮の違いを知ることが出来ました。
それぞれの地域で、今年一年の家族の幸せや無病息災を願って食べられてきたお雑煮も、他の地域と比べると違いがあって興味深いです。
今年もまだまだ知らないこと、気づいていないこと、少しずつ「てのん」でお伝えしていきます。