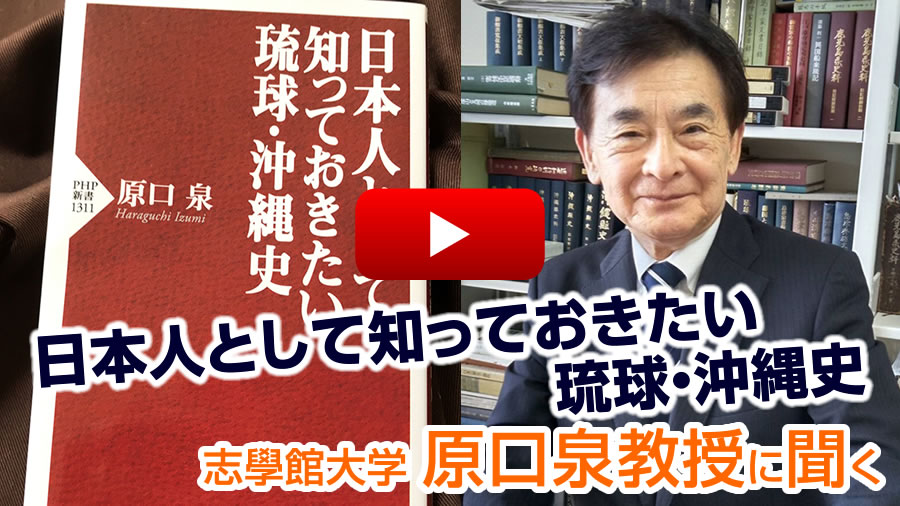家で過ごす時間が増え、普段より手の込んだ料理やパン作りに挑戦したり、親子で料理作りをする人達が増えているそう。
私も、一度作ってみたいと思っていた「かるかんまんじゅう」作りに挑戦してみました。
「かるかん」は、鹿児島を代表する郷土菓子。大好きな和菓子です。
真っ白い、ちょっとざらっとした感じの生地で、食感はしっとり、もっちりとしています。この上品な見た目や食感を出すには、きっと難しい工程があるのだろうと、作り方に興味はあってもなかなか手作りするまでには至りませんでした。
しかし、家で過ごす時間が増え、ゆっくりと時間が流れる中で、「かるかん」を作ってみようという気持ちも出てきました。
さっそくネット販売で、かるかん粉、かるかんの型、そして包装シートも注文し、材料を揃えました。
今回、はじめて認識したのですが、餡の入っていない棹菓子(さおがし)と言われる直方体の形状をしているものを「かるかん」、餡の入っているものを「かるかんまんじゅう」というそうです。
私は、「かるかんまんじゅう」の方を作ってみました。
作り方は、以下のサイトなどを参考にしました。
かるかんまんじゅうの作り方
材料・・かるかん型18個~20個分

- かるかん粉・・300g
- 長いも・・・・300g
- 水・・・・・・150cc~180cc程度
- 砂糖・・・・・240g
- 卵白・・・・・2個分
- 餡・・・・・・300g程度
※かるかん粉は、うるち米を水洗いし、半乾きさせたものを粗く粉砕したもの。
かるかん粉がない時は、上新粉で代用できます。
※使用する長芋の水分量が多い時には、水を少なめに調整します。
※卵白を使わない作り方もありましたが、長いもの粘性が少ない時は、卵白を使うとふっくら仕上がるそうなので、今回は、卵白を使って作ってみました。
- 長芋をすりおろし器ですりおろします。
- すりおろした長芋をボールに入れ、その中に、砂糖を3回に分けて入れ、その都度よくかきまぜます。

- ②の中に、水を少しずつ入れ、よくかきまぜます。長芋の水分量が多いような気がしたので、今回は、150cc程水を入れました。
- ③の中に、かるかん粉を入れ、混ぜ合わせます。

- 別のボールに卵白2個分を入れ、ハンドミキサーか泡だて器でよく泡立て、メレンゲを作ります。

- ④の中に、メレンゲを2回~3回に分けて入れ、よくかき混ぜます。これで、かるかんの生地ができました。出来上がりは、スプーンですくうと、粘性のあるぽてっとした感じです。

- 次に、かるかんの型に生地をいれます。これが、かるかんの型です。10個入り300円程度でした。

この型に、薄く油を塗って、半量程生地を入れます。

- 市販のこしあんを入れます。

- 餡が隠れるように、生地をのせます。

- 蒸し器で、20分ほど蒸します。

- 20分蒸すとこんな感じになりました。

- 少し冷めてから、竹串を使って、型からはずします。

- かるかんの出来上がりです。中に入れた餡が見えているものもありますが、市販の「かるかんまんじゅう」と同じように出来ました。


- さらに、ネットで「かるかんまんじゅう」用のシートも注文していたので(100枚で260円程度)それに包むと、なんかいい感じに仕上がりました。


- かるかんの味も、生地がしっとりもっちりしていて、とっても美味しい。難しいと思っていたかるかんまんじゅうが美味しく出来て嬉しかったです。家族からの評判も良く、「お店で買わなくても家で作れるんだね」と喜んで食べていました。ところで、かるかんの歴史ですが、今から300年ほど前から薩摩藩で作られていたといわれています。かるかんの材料となる自然薯(山芋)が多く自生していることや、琉球や奄美群島で作られている砂糖が手に入りやすいことから、その材料を主にしたかるかんが生まれたのでは?ということです。その土地でとれる産物などを生かし、昔の人たちが工夫を凝らして作ってきたものが、代々受け継がれ、その土地ならではの特産品になっていくのですね。

先日、てのんで作り方を紹介した「しんこだんご」も鹿児島のソウルフードですが、そのルーツを知ると「こういう歴史があったんだ」と驚き、改めてこれからも大事に守り伝えていきたいという気持ちが芽生えます。


鹿児島の郷土料理や、郷土のお菓子を実際に自分の手で作り、その歴史を知り、子供達やその次の世代にも伝えていけるようになりたいと思っています。
まだ作ったことのない郷土料理もありますので、これからも少しずつ挑戦していきたいと思っています。