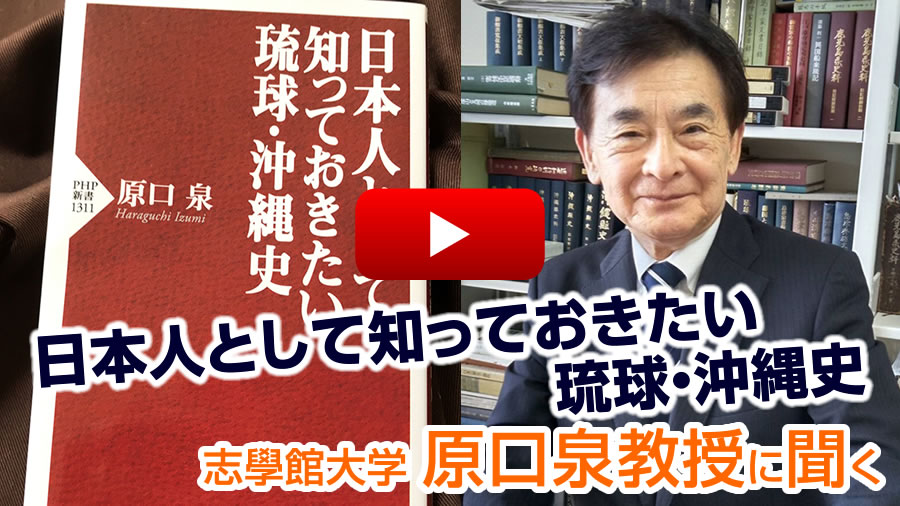大雨、台風など自然災害が発生しやすい季節になってきました。日ごろからの備えや、早めの避難など、防災への意識を持つことが大切ですよね。
そこで、雨の怖さや災害時にどう行動するべきかなど、雨の時期に読んでほしい記事を改めてお伝えします。
平成29年7月の九州北部豪雨を経験し、被災された方の話です。
昨年、九州北部豪雨の被害が特にひどかった福岡県朝倉市を訪ねました。
あちこちで重機による復旧工事が行われ、少しずつ整備も進んでいました。
しかし、まだ傾いたままの校舎があったり、それまでは人々の生活が当たり前にあった家々が土砂に埋もれたり、壊れたまま空き家になっていたり、つらい光景を多く見ました。災害により人々の暮らしが一変する事を目の当たりにし、日頃から災害に備えることの大切さを改めて感じました。
実際、災害に遭われた方々を取材し、お話を伺いました。

朝倉市の中でも、特に被害の大きかった山田交差点のすぐ近くにお住いの手嶋さんご家族に、偶然お話を伺うことが出来ました。
濁流にのみ込まれそうなご自宅から、命からがら避難されたという壮絶な経験をされていました。

テレビなどで災害に遭われた方達が「まさか、この川が氾濫するなんて」「まさか、この崖が崩れるなんて」と話されていることを耳にします。
手嶋さんも、小さい頃から1度も氾濫したことのない自宅近くの川が「まさか、氾濫するなんて」と思って、避難が遅れたそうです。
しかし最近は、短時間に狭い範囲で非常に激しく雨が降ることも多く、これまでの経験が通用しない状況も想定されます。
「まさか」ではなく、「もしかしたら氾濫するかもしれない、がけが崩れるかもしれない」と思い、早めに行動することが大切だと改めて感じます。
手嶋さん家族は、水害にあって以来、少しの雨でも避難の心構えをし、雨が多い時は早めに避難をされているそうです。
朝倉市の老舗のお菓子屋さんも被災されていました。
そこで働いてらっしゃる星野さんは、ご実家も水害で流されるという大変な経験をされながらも、災害後に取り組んだお店の浸水対策などについて前向きに話して下さりました。

朝倉に足を運んで、被害に遭われた方たちのお話を直接伺い、そこから私たちが何かを感じ、日頃の行動に生かさなければと思いました。
平成30年7月の豪雨を教訓とし、避難対策を強化するために避難勧告等に関するガイドラインが改定されています。
内閣府 防災情報のページ
昨年も記事の中で書きましたが、災害に強いまちづくりを目指すために、河川工事などハード面の整備も必要ですが、まずは、一人一人が「早めの避難」を心がける事。「自分たちの命は自分たちで守る」という自主防災の意識を持つことが、何より大切だと思います。
そして、行政などが作る防災マップをもとに、普段から避難場所や避難経路、危険個所の確認などを行う。地域に住む避難時に支援が必要な方を把握する。また、地域の避難訓練に参加するなど、日頃から一人一人の防災意識を高めておくことが大切だと思います。