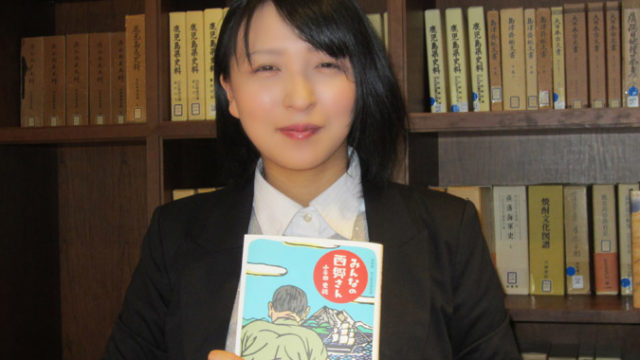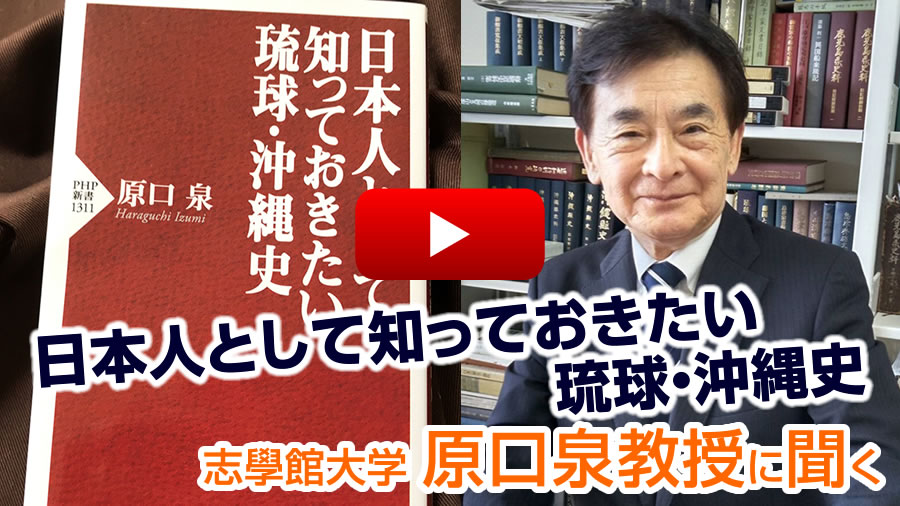2年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック開・閉会式の演出責任者に狂言師の野村萬斎さんが抜擢されました。「シンプルかつ和の精神に富んだオリパラ」を宣言。これから「和」の伝統文化が注目されそうです。
そんな中、日本の伝統的和楽器、箏の音(ことのね)の魅力を伝えたいと国内外を飛び回っている女性が鹿児島市にいます。
箏曲演奏家・梶ヶ野亜生さんです。どんな方なんでしょうか?お会いしてきました。
お約束の日、ご自宅の扉の向こうから凛とした箏の音色が響いていました。
何だか、この音を聞いているだけで癒され、雅な世界に引き込まれそう。しばらく外で聞き入っていました。その音を奏でていた方が、梶ヶ野亜生(かじがのあい)さんです。
梶ヶ野さんは、お箏(生田流筝曲)と三味線(地唄長棹)を学ぶ人たちの集まり、桐の音楽院(きりのねがくいん)を主宰しています。
ここに通っているのは、その名の通り、桐の音(箏の音、邦楽器の音)を楽しむ人たちです。
「もともと『桐の音楽院』を興したのは、母なんです。私は物心ついた頃から、お箏を教える母の傍らで、箏の音に触れながら育ちました。
遊びながら母からお箏を習って、もう3歳くらいから舞台に立っていたんですよ。(笑)母の後を継いでから、生徒さんたちにお箏を教えることが、私の大切な仕事の一つになりました。」
梶ヶ野さんのもう一つの顔が、プロの箏曲演奏家としての顔です。
凛とした和の佇まいの梶ヶ野さんですが、アーティストとしての顔は自由・闊達、とてもアクティブです。
箏デュオ~Dual KOTO×KOTO(コトコト)
その一つが、箏曲家・山野安珠美(あずみ)さんとの箏デュオ。
ふたりは共に、箏曲家・沢井忠夫、沢井一恵氏に師事。20代の頃、東京で一緒に住み込みの内弟子生活をしながら、切磋琢磨してきた同志です。
それぞれソリストとしてキャリアを積む中で、邦楽の新たな世界を切り開きたいと「箏デュオ」を結成。
各地で公演活動をしながら、「題名のない音楽会」や「邦楽のひととき」などのテレビやラジオへの出演、舞台音楽も手掛けてきました
箏の世界から新風を巻き起こす注目の邦楽アーティストなのです。
KOTO×KOTOのお二人は、ビッグなプロジェクトばかりでなく、時には、「カエルのうた」を編曲して紙芝居仕立てにして箏を奏でたり、アイディアとあそび心あふれる演出で箏の魅力を発信しています。
色々な音とつながる楽しさ
梶ヶ野さんは、箏の音(ことのね)でもっと多くの音とつながりたいと、様々なジャンルの音楽とのコラボも生んできました。
「箏は、あの凛とした音色が命。他のどんな楽器からも出せない音です。だからこそ、その音色を大事にしながら、他の様々な音と共鳴していくって、とてもワクワクします。
私の師匠、沢井先生ご夫妻(生田流箏曲院)からも、現代曲やオリジナル曲、リベルタンゴなどをさまざまにアレンジして筝の世界を広げていく醍醐味を教えていただきました。様々なジャンルとつながって新しい音楽を作っていくことは、これまでこだわり続けてきたことです。」
アウトリーチ(出向いていく)活動もまた楽しい
もう一つ大切にしているのが、すそ野を広げるためのアウトリーチ活動。
公演で訪れた土地の学校を訪問したり、小さな島の学校に行って子どもたちに箏に触ってもらったり、音を出してもらったり…箏にまだ触れたことのない子どもたちに、その魅力を体で感じてほしいと思っています。
梶ヶ野さんは、箏は「きいて」「うたって」「よんで」「つくって」和の五感を育む力がある
と話します。
「箏というと、どうしても年配の方の楽器、お正月にだけ耳にする楽器というイメージがありますが、もっと、いつでもどこでも誰でも楽しめるようになっていけばいいなぁと思います。
これまで守られてきた伝統を大切にしながらも、多くの人にとって、もっと身近で愛される楽器になってほしいです。」
母からのことづて
梶ヶ野さんは、30代半ばまで箏曲演奏家として、東京を拠点に多忙な日々を送っていました。
アメリカ、カナダ、シンガポールなど、これまでの海外公演経験は23ヵ国にも及びます。その梶ケ野さんが故郷鹿児島への帰省を決意したのは、10年前。母親の病気がきっかけでした。
「母の看病と生徒さんたちを引き継ぐために鹿児島に帰ってきました。
あの頃は、このお稽古場の隣に母のベッドを置いて、看病をしながら、隣で生徒さんたちに教え、自分の音楽活動を続けるという毎日で、一番きつかったですね。
一年後に母は亡くなりましたが、闘病中、母は病気のことを尋ねたり、桐の音学院のこれからについて私に何か「伝え残す」ことはありませんでした。でも今振り返ると、母はいつも「人のわ。人のわ」と言っていたことを思い出します。
これは「人の輪」だったのかもしれないし、和むの「人の和」でもあったのかなぁと思います。
母から、箏の音(ことのね)を通して、『人の輪』『人の和』を築いていきなさいと言われているような気がしています。」
40歳の転機。新しい働き方
東京時代、自分の目指す音楽をがむしゃらに追求してきた梶ヶ野さんは、鹿児島に帰省し、40歳を過ぎた頃、転機を迎えます。
「仕事柄、ヘルニアで腰を痛めたり、耳が聞こえなくなったり、声が出なくなったりと体の不調が出てきたんです。
知らず知らずのうちにオーバーワークになっていたんですよね。自分を見つめ直す良いきっかけになりました。
自分が一番したかったことは何だろうと問いかけて、あれもこれもではなく、自分が本当にしたいことに絞ってやっていくことにしました。
今、大事にしているのは、生徒さんたちと一緒にお箏を楽しむこと、KOTO×KOTOデュオで各地に足を運んで、待っていて下さる方々と新しい出会いをしながら、箏の音の魅力を伝えること、お箏に触れたことのない子どもたちにその楽しさを味わってもらうこと…これが今の私にフィットする音楽活動です。」
箏の音(ことのね)音楽活動の原動力は?
「私を惹きつけているのは、やっぱり「人との出会い」ですね。応援して聴いて下さる方がいる、聴きたいと待っていて下さる方々のところに出かけて行く。そんな方たちの存在に、励まされ育てられているんだなぁと最近つくづく感じます。その出会いつくってくれているのが私にとってのお箏なんです。」
梶ヶ野さんの音楽活動には、県境も国境もありません。
箏の音(ことのね)が様々な垣根を越え「人の輪」や「人の和」を作っていく力があると信じているからです。
確かなキャリアを積み上げてきたからこそ辿り着けた今。その姿を、稽古場からお母様の写真が見守っています。
去年は私生活にも大きな変化がありました。同じ和楽器の尺八を嗜む小学校の先生と結婚。人生のパートナーとの出会いもありました。
「結婚して変わったこと?夕ご飯を作らなきゃいけなくって、夕方になると慌てることかなぁ。」と、とても幸せそうです。
梶ヶ野さんは、これからも日本の伝統文化、箏の音(ことのね)の伝え手として、鹿児島を拠点に、日本の隅々、世界のあちこちを旅しながら、しなやかにその魅力を伝えていかれることでしょう。
「長く続けることが何よりも大事よ。」と言っていたお母様の声を背中に感じながら…
桐の音学院のご案内です
箏や三味線など和楽器に興味のある方は、下記の「桐の音学院」のホームページをご覧くださいね♪
※これまでは「琴」という漢字が一般的でしたが、現在では「箏」という漢字に統一されつつあります。本記事では「箏」の字に統一させて頂きました。