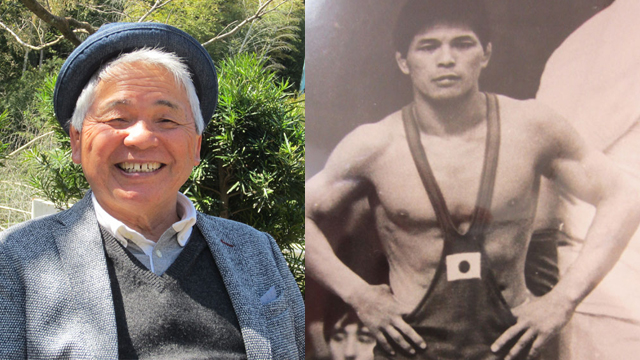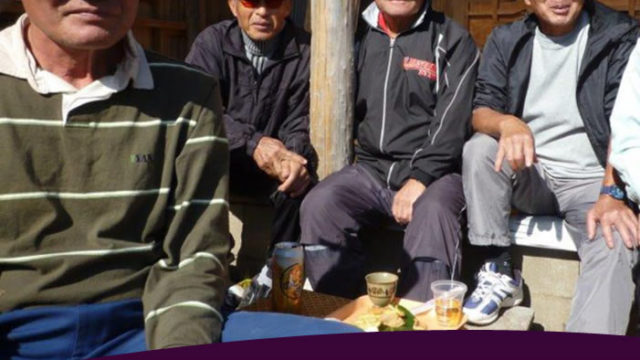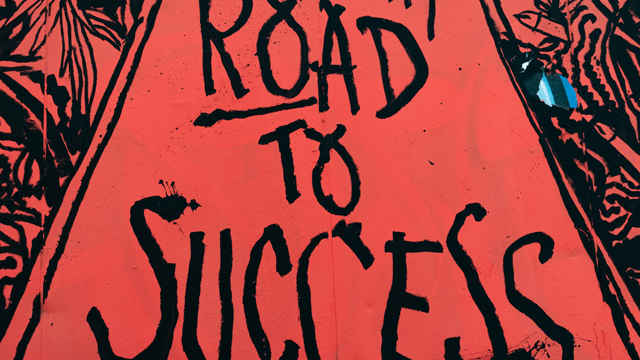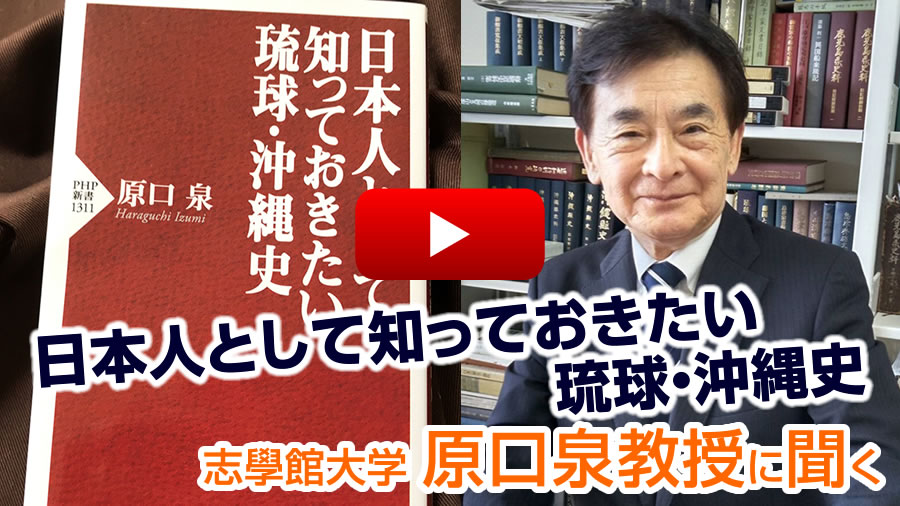近々、鹿児島市で小さな落語会が開かれるという。100人も入ればいっぱいになるという小さな会場に畳を敷き、いすを並べて開かれる手づくりの落語会。毎年この落語会を楽しみに待つファンも多いそう。
始まりは2年半前。この会への思いなど、発起人の大黒(おおくに)恂子さんに聞きました。
鹿児島での落語会。そもそもの始まりは何だったんですか?
10年ほど前にね、地元の南日本新聞に鹿児島出身のある落語家さんの話が載っていたの。
桃月庵白酒(とうげつあんはくしゅ)さん。鹿児島の進学校から早稲田大学に入って落語家になったって書いてあって、面白い人がいるもんだなぁって思って。芸人さんって支える人が必要でしょ。
私、ちょっと向こう見ずなところがあって。よ~し、この人を応援したいなぁって思ったの。
大黒さんは、早速友人たちに声をかけて、東京に桃月庵白酒(とうげつあんはくしゅ)さんの寄席を聴きに行きました。
いきなりの訪問でしたが、故郷鹿児島から応援団がやって来たと聞いて面会が叶い、以来毎年、故郷鹿児島での落語会が開かれることになったのです。「落語を愉しむ会」の旗揚げでした。
その落語を愉しむ会がまたどうして「百人で聴く落語会」を開くことになったんですか?
3年くらい前の頃だったかしら。みんなの中から、もっと誰でも気軽に、古典落語の世界に遊べるような落語会をしたいなぁっていう声があがってきて。大きなホールでの落語会はあるけれど、もっと近くで臨場感を感じながら小さな寄席の雰囲気でやってみたいと思うようになってきたんですね。
その雰囲気でやれるのが、ちょうど100人くらいかなぁって。こうして生まれたのが「百人で聴く落語会」ゆっくりと江戸の庶民の文化を味わってほしいと「ゆるいと亭」と名付けたんですよ。
嬉しかったのが、この思いに賛同してくれる若いお仲間が増えたこと。ポスター作りから、企画、運営、広報活動まで、みんな手弁当でこの会を支えているんですよ。
古典落語の世界は「丁稚(でっち)」とか「旅(はた)籠(ご)」とか江戸の庶民の暮らしが生き生きと見えてくる。落語を通して、粋な江戸の風を感じてほしいなぁって思います。
今度お呼びするのは古典落語の名手として知られる人気真打、入船亭扇辰(いりふねていせんたつ)師匠。「百人で聴く落語会」では2度目の登場です。
人情噺を得意とし、どこか昭和の職人の風情が漂う、これぞ現代のいぶし銀と言われる落語家さんです。
今回の演目は何ですか?
本来の古典落語は、予め決められた演目は無いんですよ。
最初は、枕(まくら)と呼ばれる世間話から始まって、その日のその場の観客の空気を読みながら、手持ちの50くらいの演目の中から「今日はこの話にしよう!」と決めるんです。だから、生のやりとりの中から生まれるライブ感がいっぱいなんです。
滑稽噺から人情噺の大ネタまで持ちネタも幅広く、その演技力には定評のある扇辰師匠の独演会ですから、今回はどんなお話が聴けるのか、それはそれは楽しみです。
大黒さんは、長年小学校で図書館司書を務めてきました。子供向けの図書に関わる中で、長い間、抱いていた思いがありました。
小学校の高学年になると、日本の古典芸能を学ぶ時間があるんですが、実際、生の古典芸能に触れる機会はとても少ないですよね。
たった一人が身振り手振りで噺を進め、何役も演じ分けながら、話芸の力で聴衆の想像力を膨らませ、物語の世界が広がっていく。落語って、日本が誇る伝統芸能だと思うんです。庶民の中の身近な芸能として発展してきた落語を、これからも大切にしていきたいですよね。
「100人で聴く落語会」は、テレビや大きなホールでは味わえない魅力があります。こんな機会を通して、子ども達や若い人たちにも日本の伝統文化に触れてもらって、その素晴らしさを次の世代に伝えていければと思っています。
私たちがその懸け橋になれたら嬉しいです。
江戸の風を感じながら、どうぞ、ゆるいとお楽しみくださいませ。
ゆるいと亭 百人で聴く落語会
主催:落語を愉しむ会
入船亭扇辰独演会
5月20日(日)
開演:14:00(開場:13:30)
場所:鹿児島県青年会館 艸舎
木戸銭:2,500円(学生1,000円) 当日300円増
※未就学児の入場はご遠慮下さいませ。
チケット申し込み・お問い合わせ
携帯:080-1705-2521 または
TEL/FAX:099-220-8104
大黒(おおくに)さんまで
チケット取り扱い:山形屋プレイガイド1号館5階
鹿児島県青年会館 艸舎