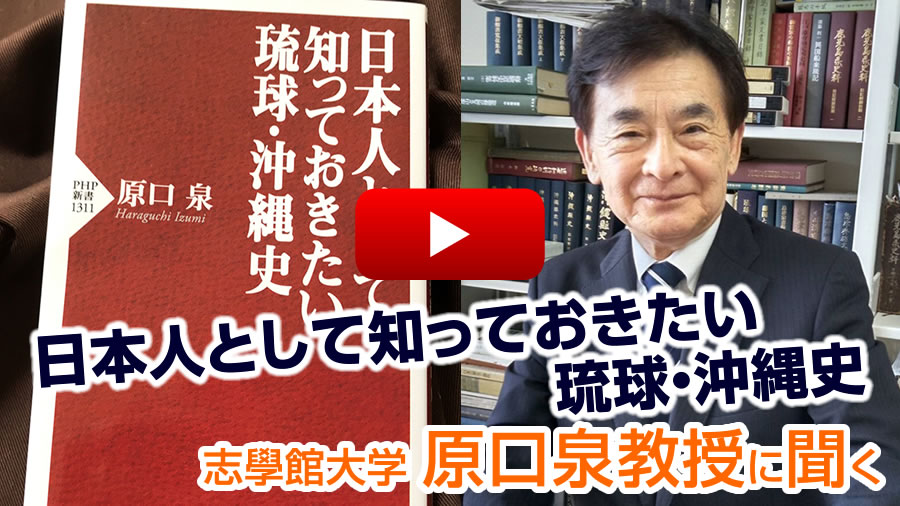「地域の見守りネットワーク」の仕掛人・澤登久雄さんに聞く
~みま~も・10年間のあゆみから~
東京・大田区で10年前から活動を続けてきたおおた高齢者見守りネットワーク「みま~も」。専門職と民間企業、行政機関が手をつなぎ、地域の高齢者が安心して暮らし続けられるまちづくりのアイディアを次々と打ち出し、形にしてきました。
その圧倒的な実践力と先進的な取り組みは全国から注目されています。国が超高齢社会を乗り切る重要政策と位置づけている地域包括ケアシステム。「みま~も」のあゆみは「地域包括ケアシステム」を具体的に形にしてきた歴史でもありました。
どうしてこんなことが実現できたのか?どうすれば、地域で支えるまちづくりが出来るのか?「みま~も」生みの親・澤登久雄さんに、その極意を伺いました。
地域包括ケアシステムとは
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供していく仕組み。
※ 地域包括ケアシステム・詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい
「地域包括ケアシステムの実現」が叫ばれて、全国各地でその取り組みを始めようとしています。でも、何から始めればいいのか?どうすればいいのか?みんな悩んでいる。まず、「みま~も」のはじめの一歩から聞かせて下さい。
当時、大田区の地域包括支援センター入新井のセンター長をしていて、毎日、高齢者の生活支援や介護、認知症など様々な問題の対応に当たっていたんです。そんな時、ふと思ったんです。ここにこうして、相談に来られる人は良いけど、ここにたどり着けない人、SOSを出せずに地域で暮らしている人がいっぱいいるんじゃないかなぁって。
それに、ここに相談に来た人の中には、もっと早くに支援が出来ていれば、ここまでにはならなかったのにという人もたくさんいました。待ってるばかりでは、本当に困っている人の今にたどり着けないんじゃないかと。そんな思いから、僕らの方が地域に飛び出すことにしたんです。
まず、何をしましたか?
仲間を募りました。たった15人からのスタート。(笑)
同じ思いの福祉や医療などの専門職、それに地元の老舗百貨店の社員さん。まず始めたのが、地元デパートのイベントスペースを使っての地域づくりセミナーでした。講師はお医者さん、看護師さん、薬剤師さん、消防や警察の人たちなど、地元の人たち。それぞれの得意分野で、健康の話、薬の話、リハビリの話など…地域の人のためになる話をしてもらいました。
「勉強になった~ためになった~」と評判が良かったです。これが地域の人たちの顔合わせの場になり、僕らにとっても、地域の課題が見えてくるきっかけになりました。あのキーホルダーもそんな中で生まれました。
もしもの時にも安心!「見守りキーホルダー」の誕生
セミナーの打ち合わせの時に、病院のソーシャルワーカーさんから救急搬送された方や認知症の方の身元が分からなくて困ることがとても多いという声があがったんです。住民の方も外出先で倒れた時、どうしよう?という不安を持っていることが分かりました。
そこでみんなの安心につながるシステムがあったら良いなぁと考えだされたのが「見守りキーホルダー」です。
このキーホルダー、事前に緊急連絡先や医療情報(病歴、薬歴など)その人にとっての重要な情報を登録してもらい、外出先での救急搬送や保護された際に、担当する地域包括支援センターが24時間体制で迅速に対応できるというものです。
でも、「包括」の日々の忙しい業務の中で、プラスアルファ―の仕事が増える。新しいシステムを持ち込むって、かなり大変なことですよね。
まずは、大田区に20ヶ所ある地域包括支援センターの中で協力がもらえた6ヶ所から始めました。そしたら、反響がすごく大きくて、これは開始から3年で大田区の正式事業になりました。
今では大田区の65歳以上の人の4人に1人にあたる4万人が登録しています。多くの人が「何かの時には助けてもらえる」という「安心」を求めていたことが分かりました。
地域づくりセミナーの開催、そこからどう発展していったんですか?
セミナーは毎月やり続けました。でも、話をする人は先生で、参加者は「それを聞きにくるお客さん」という関係が続いていて、何か物足りなさを感じていました。そんな時、駅前商店街の裏に草ぼうぼうで荒れ放題の公園を見つけたんです。
ちょうど、大田区が公園の管理を委託する「ふれあいパーク活動」を呼びかけていることを知り「みま~も」が手をあげたんです。『この公園を地域の人ときれいにしながら、みんなが集う場所が出来たら良いなぁ』と思ったんです。
すると、これまで「お客さん」だった地域の人たちが変わっていきました。あれが、最初の分岐点でした。
みま~もファームまで出来ました!
この時から、自分の地域のことが「自分ごと」になり、そこに参加することが「楽しいこと」になっていきました。すると駅前商店街の人たちが「何をしているんだろう?」と気にしてくれるようになり、今度は、商店街の空き店舗を安くで貸してくれるという話まで持ってきてくれました。商店街と繋がったことで、共同のサロン事業「みま~もステーション」がスタートしたんです。
公園と空き店舗が蘇って、みんなが集まる場所が出来たんですね…
そうなんです。そして、ここで住民主体のミニ講座が次々と生まれました。手芸や編み物が好きな人が集う手芸部、パソコンを学びたい人はパソコン教室、体を動かすのが好きな人は公園体操やポール・ウォーキング、ガーデニングや野菜づくりを楽しむ人もいます。
どれも手づくりの自主的な活動。ここで年間420講座も開催されているんですよ。
その原動力は何だったのでしょう?
「誰かから頼まれたり、やらされていること」ではないってことですよね。人はやっぱりお願いされた「やらされ感」では動かないんだなぁと実感しました。住民の中から生まれてきた自主的な活動だからこそ楽しくやれる。僕ら専門職は、それを手助けする…お互いが対等な関係です。
「みま~も」の活動に賛同し、一緒に活動してくれる協賛企業や団体もたくさんあるようですね。
協賛企業・団体は94にも上っています。医療、介護の分野だけでなく、建設、タクシー、スーパー、旅行など様々な業界からの支援があります。協賛企業には、お金を出してもらうばかりでなく、持ち回りでセミナーの運営、準備などにも関わってもらっています。
地域には様々な特技を持つ会社や団体があります。その力を「みま~も活動」で存分に発揮していただければと思いますし、住民サポーターもたくさんいるんですよ。今100名の「みま~もサポーター」いて、活動を支えています。
地域応援団「みま~もサポーター」が活躍!
みま~もサポーターは、年間2000円の登録料を払って、みま~もの活動に参加します。
登録すると、年一回体力測定を無料で受けられたり、親睦会に招待されたり、ミニ講座やミマモリ食堂のお手伝いをしたら、活動費として2時間以上で500円の地元商店街の商品券(一ヶ月2000円を上限)が支給されるという嬉しいご褒美もあります。
何よりも、地域のため、仲間のため、誰かのために、自分たちに出来ることがある!という喜びがサポーターさんたちの励みになっています。
「みま~も」はさらに進化しているそうですね。
去年5月、新たに「おおもり語らいの駅」という拠点が出来ました。ここは高齢者ばかりでなく、地域で暮らすすべての人が対象です。
ここは、僕が今勤務している牧田総合病院(澤登さんはここの地域ささえあいセンターのセンター長)が主体となってつくり、「みま~も」がこれを支える形です。
小学校の隣の身近な場所にあって、病院の看護師と医療ソーシャルワーカーが常駐しています。お茶を飲みながら、気軽に健康から育児に関する相談を受けたり、何気ないお喋りで、地域の人たちが世代を超えて交流できる「語らいの場」です。
地域で孤立しているのは高齢者だけじゃなかった!
「語らい」を始めて、困っていたのは高齢者だけじゃなかったんだということに気づかされました。
特に子育て中のママさんたち。これまで職場を中心に人とのつながりを築いてきた人たちが、出産・育児をきっかけにそのつながりを断たれ、地域の中で孤立しがちになっていました。これまで地域とのつながりがほとんど無かったという人たちが多くいました。

「語らい」には、この10ヶ月で予想をはるかに超える延べ5000人もが足を運んでいます。
「みま~も」10年のあゆみから見えてきたことは?
地域に飛び出していくと、これまで見えなかった一人ひとりの暮らしが見えてきました。
いろんな人がいて、この町が成り立っている。そんな人たちが日常的につながることで、住民主体の「気づきのネットワーク」が生まれてきました。その「気づきのネットワーク」と僕たち専門職の「対応のネットワーク」が有機的に循環していくことで、これまで専門職が点で支えていた支援が地域という面で支える力強いものになってきました。専門職と地域の人、地域のあらゆる人同士が繋がることで、「みんなで見守り、みんなで支え合う」地域づくりが形になってきました。
澤登さんたちの「みま~も」の活動は全国で反響を呼び、みま~もキーホルダーは全国各地の自治体で導入され、地方版「みま~も」も全国5ヶ所に誕生しています。鹿児島でも、去年、「みま~も・かごしま」が発足。本家に学びながら、鹿児島版「みま~も」を創り出す取り組みが始まっています。
ひたすら「人と人を繋げていく」ことを続けてきた10年。その取り組みが、確かな地域力を育み、この町で暮らす人たちに支えられているという安心感と生き生きした毎日をもたらしています。
「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること」を目指す地域包括ケアシステムの一つの理想形を見た思いがしました。人の動き出す力こそが活動の宝。
「みま~も」の実践が、我が町のこれからを考えるヒントになればと思います。
※ 今回、澤登さんのインタビュー記事掲載にあたって、おおた高齢者見守りネットワーク「みま~も」より、これまでの活動の記録写真を、多数提供して頂きました。
心よりお礼申し上げます。