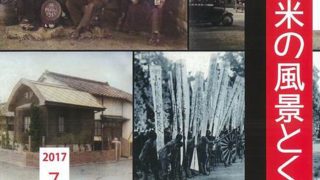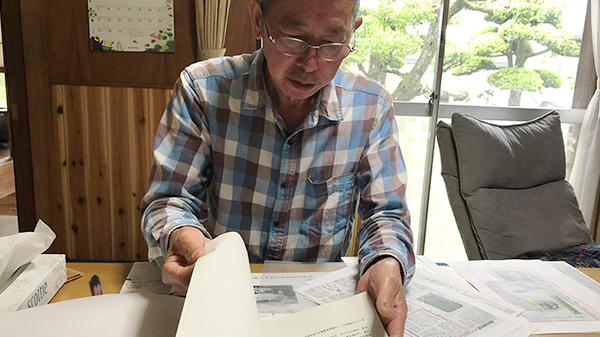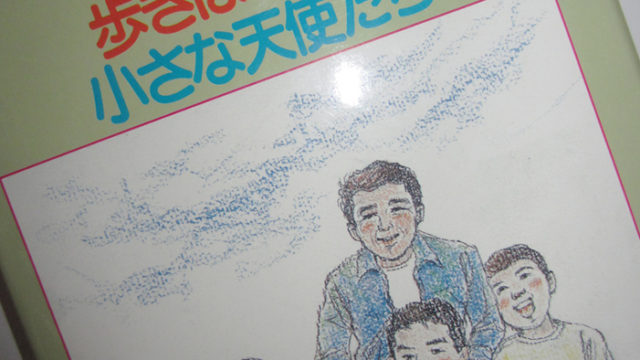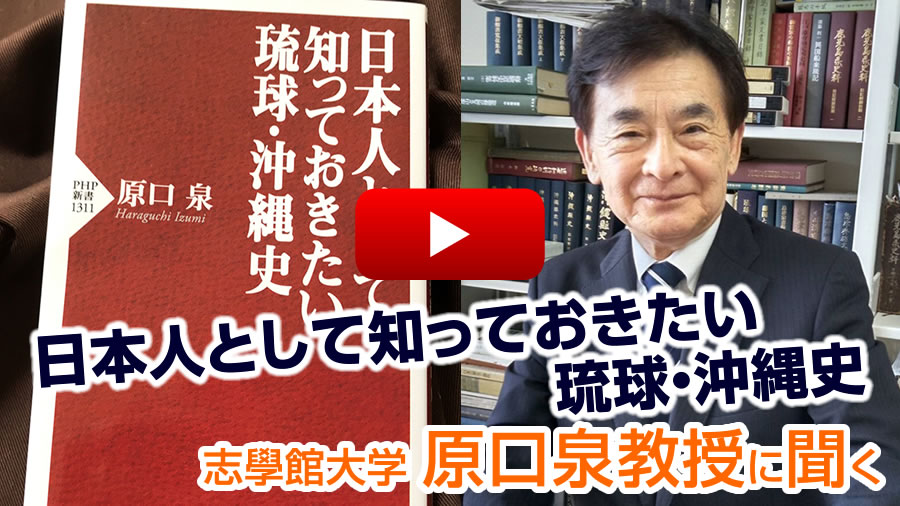きょうは終戦記念日です。
おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん…
あなたの身近にいる誰かに、戦争のお話を聴いてみませんか?
~学徒動員・名古屋で戦闘機をつくっていました~
昭和16年、太平洋戦争が始まった時、私は13歳でした。
当時日本は軍事一色で、お国のために戦っている兵隊さんがとても誇らしく映り、子ども心に、「日本は強い、負けるはずは無い」と思っていました。
昭和18年、先生になりたくて鹿児島師範学校に入学しました。でも、2年生の頃には勉強どころではなくなっていました。
制服を動きやすいモンペに履き替え、毎日、食糧増産のための勤労奉仕に励みました。
兵隊さんが次々に出征し、男手がいなくなっていたので、留守家族の農作業の手伝いもしました。
「兵隊さんが戦地で頑張っているのだから、私たちも頑張らなくては…」という気持ちで、きついなんてちっとも思いませんでした。
今にして思うと、日本の戦況は大変厳しくなっていた頃ですが、そんな情報はちっとも入ってきませんでした。
戦地での兵隊さんが不足していたんでしょう、戦地に学徒まで動員されるようになっていきました。そんな中、鹿児島師範学校の私たちにも軍需工場へ行くようにという命令が下ったのです。昭和20年の事です。
1月の寒い夜、鹿児島駅から夜行の貸切列車に乗って名古屋へと向かいました。
当時、名古屋はもっとも空襲が激しく危険な場所と言われていました。両親と別れの水盃を交わして出発してきた友達もいました。
名古屋に着くと、その日から、戦闘機づくりが始まりました。
「神風」と書かれた鉢巻きを締め、防空服に身を固め、軍歌「勝利の日まで」を歌いながら毎日、宿舎から工場まで向かいました。
仕事は、ジュラルミンにドリルで穴を開け、空気ハンマーで的確に鋲を打ち込む作業。ただひたすらその作業を続け続けましたが、次第に手がしびれ、感覚が無くなり、字も書けなくなりました。
空襲は昼夜問わずあり、入浴中髪にシャンプーをつけたまま気のみ気のままで防空壕に逃げ込んだ事もあります。空襲警報が鳴ると、お守りを握りしめて走る人、南無阿弥陀仏を唱える人…
皆必死で逃げました。機銃の撃ち込まれる音、叫び声は今も耳に焼きついています。
防空壕は排水が悪く、冷たい雪解け水が溜まっていて、腰まで浸かりながら身を潜めていました。手足はしもやけで腫れ上がり。皮膚も破れて辛かったです。
ある日、撃ち落されたアメリカのB29を見に行ったことがあります。
すると銀色の胴体にマリリンモンローを思わせる金髪のモダンガールが大きく描かれていました。赤い唇にハイヒール。私たちはモンペ姿に竹やり。何という違いでしょう。
余裕綽々のアメリカを見たような気がして、底知れぬ不安がよぎりました。
終戦間近の頃になると、友軍機も姿を見せなくなりました。
私たちが作った戦闘機は完成しても、どこに運ばれる事もなく並んだままでした。
燃料が無くて飛び立てなかったそうです。
そしてその戦闘機が米軍の空爆を受けていました。
私たちは一体何をしているの?不安がとても大きくなりましたが、終戦の日を迎えるその日までただひたすら「お国のために」と思いながら戦闘機を作る日々でした。
知らないこと、知らされないことの怖さを改めて感じます。
私たちは幸い、ひとりの犠牲者を出すこともなく鹿児島に帰ることが出来ました。
それは奇跡のようにも感じられます。
私は生き残ったことで、念願の中学校の教員としてスタートすることが出来ました。
でも、そうしたくても出来なかった人たちがたくさんいました。
労働力不足を補うために300数万人の学徒が勤労奉仕に動員され、1万人余りの学徒が戦禍に倒れたと言います。その事を思う時、胸が痛みます。
犠牲を負ったのは、敵国も同じだったに違いありません。

今、自由に学べる時代が来ました。その喜びをかみしめながら、
学びたかったけれど学べなかった、
生きたかったけれど生きられなかった人たちに代わってお伝えしたいです。
たくさんの人の人生を奪ってしまう戦争を二度としないで下さい。
そしてもう一つ、お伝えしたいことがあります。
私たちはあの戦争で何もかも無くしました。
焼け野が原となった故郷はゼロからのスタートでした。
みな生きるために必死に立ち上がろうとしていました。
私たちは学びたい一心で、焼けて無くなった学校の再建に動き出しました。
むかしむかしの鹿児島女子の逞しい学校再建の物語。
それはそれは懐かしい思い出です。
今度またいつか、そのお話をいたしましょう。